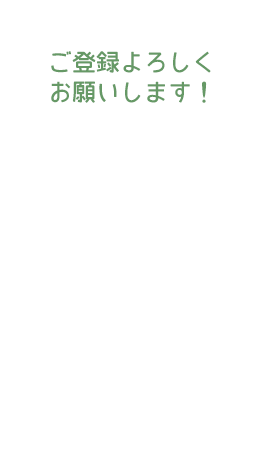わたし語の広場
企画・制作・運営:
チーム・もっとつなぐ
チーム・もっとつなぐは、ドイツの様々な学びの場で活動している日本語教師の集まりです。 複言語キッズの「ことば」と「こころ」の育ちについて複言語・複文化の視点をもって多くの人たちと考えるために、2015年よりドイツ国内外でワークショップや講演会を実施してきました。その成果をまとめたのが、『わたし語ポートフォリオ』です。ドイツ語訳のついたドイツ版のほか、各国・各地のバージョンをダウンロードしていただけます。『わたし語ポートフォリオ』の輪を一緒に広げていきましょう!
※現在ダウンロードいただけるのは、ドイツ版、オーストラリア版、フランス版です。

『わたし語ポートフォリオ』
オンライン公開版制作/
勝部 和花子、札谷 緑、田川 ひかり、松尾 馨、三輪 聖
わたし語と聞いて、
何を思い浮かべますか?
「わたし語」は・・・ことばの「とんぼ玉」。
- 自分の中にある複数のことばが混ざり合ったもの。
- 十人十色。 「とんぼ玉」のように一人ひとり異なる混ざり方 をしています。
- 成長とともに変化します。
- 「とんぼの目」のような複眼的なものの見方を促します。
【とんぼ玉】
 2色以上の色ガラスを練り込んでできたもの。模様のついたガラス玉がトンボの複眼に似ていることから、そう呼ばれています。
2色以上の色ガラスを練り込んでできたもの。模様のついたガラス玉がトンボの複眼に似ていることから、そう呼ばれています。
【とんぼの目】
 トンボの複眼は、ハチの巣のような六角形の目が集まってできていて、その数は1万個から3万個にもなります。
トンボの複眼は、ハチの巣のような六角形の目が集まってできていて、その数は1万個から3万個にもなります。

日本語という色が加わることで、子どもたちの「わたし語」が豊かになります。
そして、豊富な言語レパートリーが、一人ひとりの「わたし語」をより輝かせます。
 「わたし語」は、家族のことば、住んでいる国や地域のことば(方言など)、学校で習い始めた外国語、好きなアニメのキャラクターのことばなど、これまで複言語キッズが自分の中に取り入れてきたさまざまな「ことばのレパートリー」が混ざり合ってできています。
「わたし語」は、家族のことば、住んでいる国や地域のことば(方言など)、学校で習い始めた外国語、好きなアニメのキャラクターのことばなど、これまで複言語キッズが自分の中に取り入れてきたさまざまな「ことばのレパートリー」が混ざり合ってできています。
それはまさに、いろいろなことばでできた十人十色の「とんぼ玉」。みなさんのお子さんの「わたし語」というとんぼ玉の中には、すでに「日本語」という色と模様が溶け込んでいることでしょう。
輝く「わたし語」をもつ複言語キッズは、まるで空を舞うトンボのように、
異なる文化やことばの境界を越え、周囲とつながり、周囲をつなげる力を秘めています。
『わたし語ポートフォリオ』をはじめませんか?
『わたし語ポートフォリオ』は、親子が家庭でいっしょに取りくむ「ことばの育ち」の記録帳です。人生とともに変化していく、親子それぞれの「わたし語」を見つめます。 およそ5歳から10歳の複言語キッズを対象にしています。「複言語キッズ」は、毎日の生活の中で二つ以上のことばと文化に深いつながりをもっている子どもたちのことです。
「ポートフォリオ」って?
もともとはアーティストが自分の作品を入れて、それを人に見せるためにファイリングしたもの。最近では世界各地の教育現場で、「学びと体験のプロセス」を記録するためにも用いられています。
『わたし語ポートフォリオ』3つの柱
わたしのプロフィール
「わたし語」を見える化します。自分の「中」や「周り」にあるさまざまなことばや文化について考えをめぐらし、「自分を作っているいろいろなもの」を見つめます。
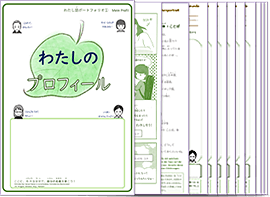
できることファイル
子どもたちが日本語を使って「できること」を集めます。また、日本の文化やことばだけでなく、異文化との比較をとおして、「知っていること」「思っていること・考えていること」などを記録していきます。
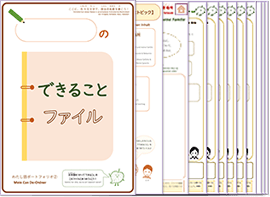
わたしの作品集
これまでに日本語で書いたもの・作ったもの・体験したことなど、子どもたちと日本(語)とのつながりを表わす作品を集めていきます。
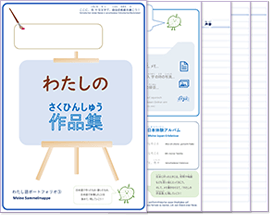
◎「みんなの作品集」はこちらから
ご覧いただけます!
使い方は
『わたし語ポートフォリオ』
活用ガイドで●ポートフォリオ3種の使い方の説明
●複言語キッズの「わたし語」を育てる5つのポイントの提案
●ヨーロッパの言語教育理念の分かりやすい説明
●おすすめの文献とリンクの紹介
ポートフォリオのオンライン公開までご支援、ご協力いただいた方々
チームアドバイザー:奥村三菜子、野山広、福島青史
イラストレーター:横山 愛
特別協力: ドイツ共益社団法人日本文化普及センター
ご協力・ご支援くださった方々(順不同): 国際交流基金ケルン日本文化会館、こども日本語クラブでんでんむし(2021年2月現在、デュースブルク日本語学校でんでんむしとして登録申請中)、株式会社アスク出版、JPT EUROPE LTD. (JP BOOKS)、ドイツで育つ子供たちのための継承語教育を考える会、ニュルンベルク日本語研究会(フランケン勉強会)、Bildungszentrum im Bildungscampus Nürnberg、過去のワークショップ参加者の皆さん、パイロット版にご意見くださった方々